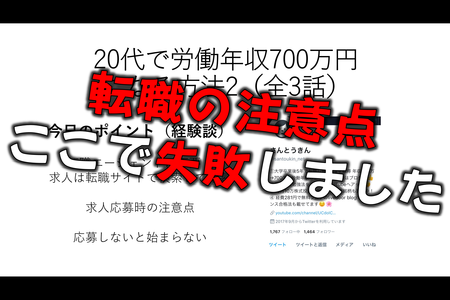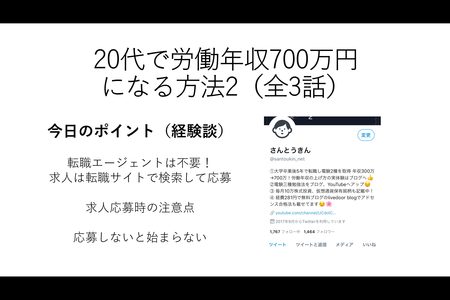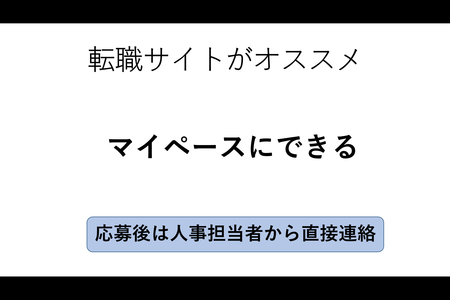こんにちはさんとうきんです。今回は 【電気主任技術者のお財布事情】さんとうきんの現在の家計簿と資産運用についてやっていきたいと思います。家族4人の家計簿を公開することでこれから外資転職や結婚する場合に参考にしてもらえればと思います。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
これからも電験、転職に関して動画作っていくので良かったらチャンネル登録お願いします。
主に3つ順を追って解説します。一つ目一か月の生活費、二つ目年収、外資系資産運用でやっていきたいと思います。
・一か月の生活費
まずは一か月の生活費ですが、家賃:8万 食費6万 車5万 水道光熱費2.5万 日用品2万 子供2万 保険1.5万 通信費1万 奨学金1万 その他1.5万でざっくり毎月30万円程度になります。
家賃ですが13年間は毎月1万以上帰ってくるので実際はもう少し安いかもしれませんが固定資産税やメンテナンス費用を考えるとそこはノータッチで計上しています。
食費は自分の昼食も含めて大体毎月6万円ほどになってそうです。毎月外食1回分もここに含めているので多すぎることはないですが人数が増えてきたのでママの弁当生活にしようか検討中です。
光熱費は電気料金の値上げで激増中ですが賃貸よりはかなり安くなりました。30年使うとすると屋根上ソーラー分でもう5000円ほど毎月浮きそうです。
・収入
続いて収入ですが、毎月50万円使えるお金があります。配当や副業も微々たる金額ですが数万円あるので足しにはなっています。ここで5~10万円作れると坊ちゃんの教育費が激増してもやっていけそうですが、このままだとトントンになる可能性があります。特に高校生、大学生になると塾や学費で生活費が45万円以上になるので子供が3人4人になると赤字になるので対策検討中です
子供手当もあり来年はゲットできそうで毎月3万円程度が収入として加わるのはかなり大きいです。しかし、控除が全くないので1000万円を超えてくると一切控除されないのは本当に子ども増やす気はなさそうです。
・資産運用
続いて資産運用ですが、収入50万円から生活費30万円を引くと毎月20万円ほど余りが今のところあります。年々生活費が上がっているのでこんなに余っているのは今だけかもしれませんが、人数が増えてもやっていけるようにインデックス投資にぶち込んでいきます
一例として毎月20万円を年利5%で20年運用していくと8220万円になるということでこれくらいあると4人くらいいても生活がきついときは取り崩しても問題朝そうです。
これ以外にも家のメンテナンスをインデックス投資に入れるとどうなるか見ていきます。毎月1万円を年利5%で20年運用していくと411万円になります。現金だけで賄おうとするとなかなか難しいかもしれませんが、インデックス投資を使うことで費用は抑えれそうです。
今検討しているのは保険金をインデックス投資にぶち込むことを10年程度ではじめたいなと思っています。切り替えた直後に病気になる可能性もあるのでそこだけは対策しなければないですが、保険だと戻ってこないものがインデックス投資だと全額戻ってくるし金額も増えるかもしれません。
今だと1.5万円を利回り5%で30年間、家族全員分の保険金としてインデックス投資に入れると1248万円にもなります。ただし住宅ローンがあるのと、年金保険の相性がいいと思うのでしばらくはこのまま様子見していきます。
住宅の支払い分として3600万円の年金保険で毎年180万円ずつ減額するプランで資産が少ない若いときに保険金額が多いので個人的には気に入っている保険です。
人生100年時代だと保険にかけてる金額が膨大な金額で、さっきの想定は保険加入期間が30年で1248万円ですが、60年として計算しなおしてみます。利回り5%だと15年で2倍なのでさらに30年だと5000万円が保険に消えていきます・・。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。外資転職や高収入サラリーマンが話題になりますがそれ以上に保険の使い方、補修費用の運用などの見直しで人生を大きく転換できる可能性があるのではないかと個人的には考えています。
一方で株は個別株だとリスクが大きすぎるので用途に応じて基本的にはインデックス投資をメインにしないと増えると持っていたものが無くなるリスクもあるので注意したいところです。
今回は以上になります。動画詳細欄に投資サブチャンネルあるので良かったらご覧ください。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
これからも電験、転職に関して動画作っていくので良かったらチャンネル登録お願いします。
主に3つ順を追って解説します。一つ目一か月の生活費、二つ目年収、外資系資産運用でやっていきたいと思います。
・一か月の生活費
まずは一か月の生活費ですが、家賃:8万 食費6万 車5万 水道光熱費2.5万 日用品2万 子供2万 保険1.5万 通信費1万 奨学金1万 その他1.5万でざっくり毎月30万円程度になります。
家賃ですが13年間は毎月1万以上帰ってくるので実際はもう少し安いかもしれませんが固定資産税やメンテナンス費用を考えるとそこはノータッチで計上しています。
食費は自分の昼食も含めて大体毎月6万円ほどになってそうです。毎月外食1回分もここに含めているので多すぎることはないですが人数が増えてきたのでママの弁当生活にしようか検討中です。
光熱費は電気料金の値上げで激増中ですが賃貸よりはかなり安くなりました。30年使うとすると屋根上ソーラー分でもう5000円ほど毎月浮きそうです。
・収入
続いて収入ですが、毎月50万円使えるお金があります。配当や副業も微々たる金額ですが数万円あるので足しにはなっています。ここで5~10万円作れると坊ちゃんの教育費が激増してもやっていけそうですが、このままだとトントンになる可能性があります。特に高校生、大学生になると塾や学費で生活費が45万円以上になるので子供が3人4人になると赤字になるので対策検討中です
子供手当もあり来年はゲットできそうで毎月3万円程度が収入として加わるのはかなり大きいです。しかし、控除が全くないので1000万円を超えてくると一切控除されないのは本当に子ども増やす気はなさそうです。
・資産運用
続いて資産運用ですが、収入50万円から生活費30万円を引くと毎月20万円ほど余りが今のところあります。年々生活費が上がっているのでこんなに余っているのは今だけかもしれませんが、人数が増えてもやっていけるようにインデックス投資にぶち込んでいきます
一例として毎月20万円を年利5%で20年運用していくと8220万円になるということでこれくらいあると4人くらいいても生活がきついときは取り崩しても問題朝そうです。
これ以外にも家のメンテナンスをインデックス投資に入れるとどうなるか見ていきます。毎月1万円を年利5%で20年運用していくと411万円になります。現金だけで賄おうとするとなかなか難しいかもしれませんが、インデックス投資を使うことで費用は抑えれそうです。
今検討しているのは保険金をインデックス投資にぶち込むことを10年程度ではじめたいなと思っています。切り替えた直後に病気になる可能性もあるのでそこだけは対策しなければないですが、保険だと戻ってこないものがインデックス投資だと全額戻ってくるし金額も増えるかもしれません。
今だと1.5万円を利回り5%で30年間、家族全員分の保険金としてインデックス投資に入れると1248万円にもなります。ただし住宅ローンがあるのと、年金保険の相性がいいと思うのでしばらくはこのまま様子見していきます。
住宅の支払い分として3600万円の年金保険で毎年180万円ずつ減額するプランで資産が少ない若いときに保険金額が多いので個人的には気に入っている保険です。
人生100年時代だと保険にかけてる金額が膨大な金額で、さっきの想定は保険加入期間が30年で1248万円ですが、60年として計算しなおしてみます。利回り5%だと15年で2倍なのでさらに30年だと5000万円が保険に消えていきます・・。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。外資転職や高収入サラリーマンが話題になりますがそれ以上に保険の使い方、補修費用の運用などの見直しで人生を大きく転換できる可能性があるのではないかと個人的には考えています。
一方で株は個別株だとリスクが大きすぎるので用途に応じて基本的にはインデックス投資をメインにしないと増えると持っていたものが無くなるリスクもあるので注意したいところです。
今回は以上になります。動画詳細欄に投資サブチャンネルあるので良かったらご覧ください。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。